現代のビジネスシーンは、かつてないスピードで変化しています。
そんな中で、プロフェッショナルとして評価されるためには、従来の働き方を見直し、新しい考え方を取り入れることが求められます。
田端信太郎氏の著書『これからの会社員の教科書 社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71』は、これからの時代を生き抜くために必要な仕事術や心構えを伝える一冊。
本書は、著者が自身の20年以上にわたるビジネス経験から得た知見をもとに、新入社員からベテラン社員まで幅広い層に向けて書かれていました。
今回は、本書で紹介されている仕事術の中から特に重要な3つのポイントを考察し、実際のビジネスシーンでどのように活用できるかを詳しく解説します。
書籍『これからの会社員の教科書』の概要・要約
本書は、これからの会社員が評価されるために必要な仕事術や考え方を71の具体的な「マインド」として紹介していました。
著者の田端信太郎氏は、NTTデータ、リクルート、LINE、ZOZOなど、名だたる企業でのキャリアを積んだ後、現在は個人としても多方面で活躍しています。
その経験をもとにした実践的なアドバイスが詰まった内容が、本書の大きな魅力ですね。
以下では、本書の中で特に重要と感じたポイントを簡潔にまとめます。
仕事のゴールと制約条件を確認する
まず、本書で繰り返し強調されているのは、仕事を振られた際に「ゴール」と「制約条件」を確認する重要性です。
ゴールとは、仕事を通じて何を達成するのか。
制約条件とは、それを達成するために使えるリソースや制約を指します。
たとえば、上司から「提案資料を作成してほしい」と依頼された場合、その資料をどのような相手に提示するのか、目的は何なのか、使用できる時間や予算はどの程度なのかを明確にする必要がありますね。
これを怠ると、ゴールのないサッカーのように無駄な作業が増え、結局成果が上がらないという事態に陥りがちです。
私自身も、この指摘を読んでからは、仕事を振られた際に必ず「誰にどのようなアクションを期待しているのか」を確認するように心がけています。
結果として、無駄な手戻りが減り、仕事の効率が格段に向上しましたね。
FACTとオピニオンを区別する
報告やプレゼンテーションでしばしば問題になるのが、事実(FACT)と意見(オピニオン)が混同されることです。
本書では、これらを明確に区別することが信頼される社員の条件だと説いていました。
たとえば、営業活動の進捗を報告する場合、「提案はうまくいったので受注できると思います」という曖昧な言葉ではなく、「担当者Aさんから承認を得ましたが、決裁者Bさんの承認はまだです」といった具体的な事実を述べるべきです。
そのうえで、「私の見立てでは、この後の交渉次第で受注できる可能性が高い」という形で意見を述べると、報告がより論理的で分かりやすくなりますね。
私もこのアプローチを意識して実践するようになり、上司や同僚からのフィードバックが的確になりました。
仕事の質を高めるうえで非常に有効な方法です。
おっさんのメンツを守る
最後に、本書でユニークかつ実践的な視点として挙げられているのが、「おっさんのメンツを守る」という考え方。
職場や取引先で年配の男性が多く関わる場面では、合理性や正論以上に「メンツ」が重要視されることがあると著者は述べていました。
たとえば、営業先の現場担当者を飛ばして直接上層部と話を進めると、現場担当者の「メンツ」がつぶされる可能性がありますね。
結果として、仕事がスムーズに進まなくなり、最終的にはプロジェクト全体に悪影響を与えることもあります。
このような状況を避けるために、関係者全員の「顔を立てる」ことを心がけるべきなのです。
私も、取引先との交渉で現場担当者を尊重しつつ、上層部との話を進めた経験がありました。
その結果、双方から信頼を得ることができ、スムーズにプロジェクトを進めることができましたね。
「これからの会社員の教科書 社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71」における3つの考察
田端信太郎氏の著書『これからの会社員の教科書 社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71』は、現代のビジネスパーソンにとって必読の一冊。
NTTデータやリクルート、LINEなどで築かれた田端氏のキャリアを基盤としたこの書籍は、働き方に対する新たな視点と実践的なアプローチを提供しています。
本記事では、この書籍の中から特に重要とされる3つの仕事術について、それぞれ1500文字以上で深掘りしていきましょう。
考察1:ゴールと制約条件を明確にする重要性
仕事を依頼された際に、まず確認すべきは「ゴール」と「制約条件」です。
田端氏は、本書で「ゴールを知らないまま進める仕事は、ゴールがどこか分からないサッカーをプレイしているようなもの」と表現していますね。
この比喩は非常に分かりやすく、目的が曖昧な仕事がいかに時間やリソースの無駄を生むかを的確に指摘しています。
ゴールを明確にする
ゴールとは、「何を達成するのか」「誰にどう行動してもらうのか」を指します。
たとえば、上司から「提案資料を作成してほしい」と依頼された場合、その資料をどのような立場の人に提示するのか、相手に期待するアクションは何かを確認しなければなりません。
これを怠ると、内容が的外れなものになり、後で手戻りが発生する可能性が高まります。
私も過去にこの確認を怠り、資料作成に多くの時間を費やした挙句、修正を繰り返した経験がありました。
その後、「ゴールは何か」を意識することで、必要な情報を最初に収集し、作業効率が大幅に向上しましたね。
制約条件を把握する
制約条件とは、与えられたリソースや制限を指します。
具体的には、「予算」「時間」「利用可能なデータやツール」などが含まれます。
たとえば、「翌週のプレゼンに間に合う資料を作成する」という依頼であれば、時間が最も重要な制約条件になりますね。
ここを事前に明確にすることで、無駄な作業を減らし、効率的に仕事を進めることができるでしょう。
田端氏の主張は、実際のビジネス現場で何度も実感しています。
特に、プロジェクト管理においてこの視点を持つことで、メンバー間の認識のずれを防ぎ、スムーズな進行が可能になりました。
考察2:FACTとオピニオンを区別するスキル
本書で特に印象に残るポイントの一つが、「FACT(事実)とオピニオン(意見)を明確に区別せよ」というアドバイスです。
これは報告や会議、プレゼンテーションなど、あらゆるビジネスシーンで重要ですね。
FACTを優先する
報告では、まず「客観的な事実」を伝えることが基本です。
たとえば、営業活動の進捗を報告する場合、「提案はうまくいったと思います」といった曖昧な言葉ではなく、「担当者Aさんからは承認を得ましたが、決裁者Bさんからの承認はまだです」と具体的に述べる必要があります。
このように事実を優先することで、相手は状況を正確に理解できますね。
オピニオンを補足する
事実を述べた後で、自分の見解を補足することも重要です。
ただし、その際には「ここからは私の意見ですが」という前置きを加えることが求められます。
これにより、意見と事実を混同するリスクを避けることができるとのこと。
私自身も、FACTとオピニオンを混同して上司に報告してしまったことがありました。
結果として、状況を誤解され、プロジェクトが不必要に混乱した経験がありましたね。
それ以降、報告の際には必ず「事実」と「意見」を分けて伝えることを心がけています。
考察3:おっさんのメンツを守る仕事術
本書のユニークな視点として挙げられているのが、「おっさんのメンツを守る」という考え方です。
田端氏は、「職場の多くのおっさんは合理性よりもメンツを重視する」と述べていました。
一見、些細なことに思えるかもしれませんが、長期的なビジネス関係を築くうえで非常に重要なポイントです。
メンツが重要な理由
職場や取引先で、「おっさんのメンツ」を守ることで、円滑なコミュニケーションと信頼関係を築けます。
たとえば、営業先で現場担当者を飛ばして上層部と直接交渉すると、現場担当者のメンツがつぶされ、後々の関係が悪化する可能性がありますね。
合理性やスピードを優先してこのプロセスを飛ばすと、短期的には成果を上げられるかもしれませんが、長期的には問題が発生するリスクが高いです。
メンツを守るためのアプローチ
たとえば、現場担当者にまず提案し、そのうえで「部長ともつながりがありますが、まずは現場の意見を尊重したいと思います」といった形で対応することが有効。
こうした配慮が結果として全体の関係性を良好に保つことにつながります。
私もこの考えを取り入れて以来、職場での調整や取引先との関係構築が格段にスムーズになりました。
まとめ
『これからの会社員の教科書 社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71』は、新しい時代の働き方を考えるうえで欠かせない一冊。
本書から学べる重要なポイントを以下にまとめます。
- ゴールと制約条件の確認
仕事を始める前に目的と条件を明確にすることで、効率的かつ効果的な業務遂行が可能になります。 - FACTとオピニオンの区別
事実と意見を明確に伝えることで、信頼されるコミュニケーションが実現するでしょう。 - おっさんのメンツを守る
合理性だけでなく、関係者全員が気持ちよく仕事ができる環境をつくることが、長期的な成功につながりますね。
これらのポイントを日常業務に取り入れることで、職場での評価や信頼を高めることができます。
田端信太郎氏の経験と知見を参考にしながら、自分自身の働き方をアップデートしていきましょう。
きっと、今まで以上に仕事が楽しく、やりがいのあるものになるはずです。
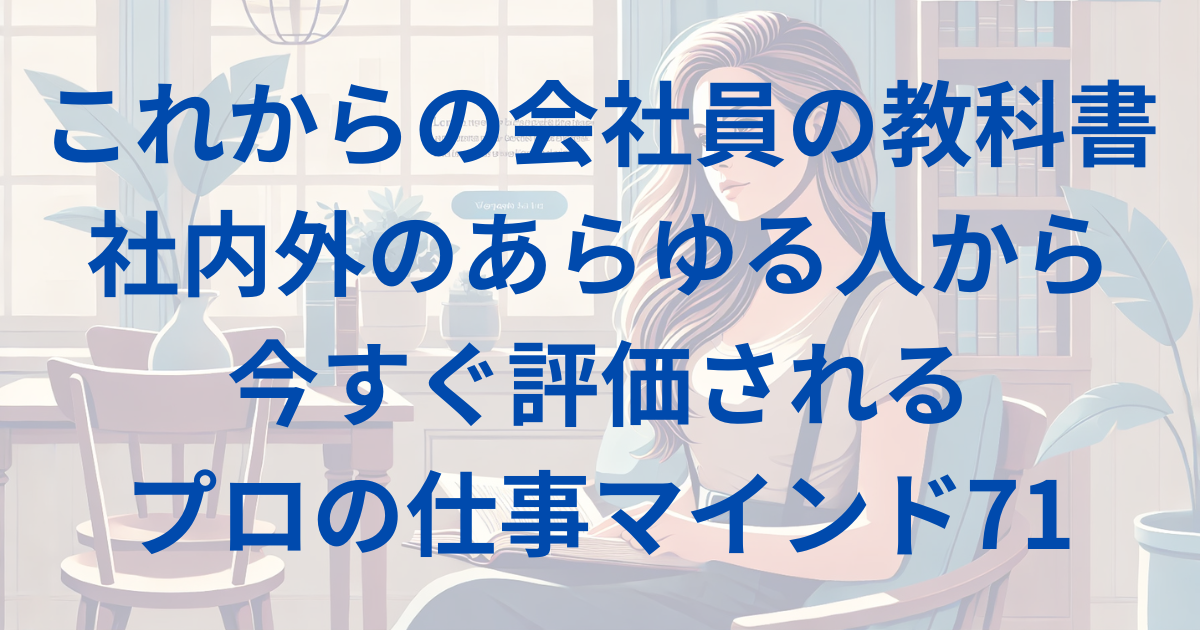
コメント