日々の生活や仕事で、「言いにくいこと」を伝えなければならない場面は誰にでもありますよね。
率直に言うと角が立つし、相手との関係性を壊すリスクもあります。
かといって、我慢を続けるのも自分の心に負担がかかります。
そんなときに役立つのが、中野信子さんの著書『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』。
本書では、京都人の洗練されたコミュニケーション術と脳科学の視点から、「いけず(遠回しな嫌味)」を上手に活用し、相手との良好な関係を保ちながら意見を伝える技術が紹介されています。
この記事では、本書に触れながら、伝え方を変えるための3つの知恵について考察していきましょう。
書籍『エレガントな毒の吐き方』の概要・要約
本書は、京都人特有の間接的で洗練されたコミュニケーションを題材に、言葉を選ぶ技術を深掘りしています。
著者は「ストレートな言葉ではなく、相手に考えさせる遠回しな表現」を用いることで、人間関係を円滑にしながら自己表現を行う方法を提案していました。
以下では、本書の核心となるポイントをいくつか要約します。
京都式コミュニケーションの本質
京都人の言葉遣いは、直接的な表現を避けながらも、相手に意図を汲み取らせる「間接的な伝え方」にあります。
たとえば、「お嬢さん、ピアノが上手ですな」という一見褒めているような言葉には、「音がうるさい」という真意が隠されています。
こうした遠回しな表現は、相手との関係性を壊さずに意図を伝えるための重要なスキルであるとのこと。
さらに著者は、「本音を無理に伝えることよりも、関係性を優先することが時に大切である」と指摘していました。
長期的な視点で考えると、本音をストレートにぶつけることが最善とは限りません。
言いにくいことを伝える3つのレッスン
本書では、京都式コミュニケーションを実生活に活かすための具体的なレッスンが紹介されています。
レッスン1:褒めているように見せかける
「褒める」ことをベースにしつつ、相手に真意を汲み取らせる技術です。
たとえば、パワハラ上司に対して。
「そうおっしゃっていたとは気づきませんでした。〇〇さんはそんな合理的なやり方を思いつくなんて、さすがですね」
と言うことで、直接的な反論を避けつつ、相手に気づきを促す方法が提案されています。
このテクニックを用いると、相手に不快感を与えずに、自分の意図を伝えられる可能性が高まりますね。
レッスン2:遠回しな質問で相手に考えさせる
京都人特有の「疑問形を活用した伝え方」が紹介されています。
たとえば、「ドアを開けっぱなしにしていると、誰か来るの?」という遠回しな質問は、ドアを閉めてほしいという意図を柔らかく伝える例として挙げられていますね。
疑問形を使うことで、相手に「自分で考えさせる」きっかけを与えます。
レッスン3:オウム返しで受け流す
デリケートな話題や不躾な質問には、「オウム返し」が効果的。
たとえば、「子供いないの?」という質問に対して、「子供いないの?っておっしゃいましたね」と一旦繰り返すことで、相手の無遠慮な質問に反省を促す効果がありました。
このテクニックは、相手に言葉の重みを意識させる点で非常に有効です。
書籍『エレガントな毒の吐き方』における3つの考察
『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』は、単なる「嫌味」を超えた洗練されたコミュニケーション術を学ぶための指南書。
日常の中で、言いたいことをどう表現するか悩む場面は多くありますね。
ストレートに伝えればトラブルの元となり、言わずにいると自分が疲弊してしまいます。
そんな悩みに対し、本書は京都人の伝統的な表現方法と脳科学の視点を掛け合わせ、エレガントな言葉遣いを提案しています。
今回は本書から特に重要なポイントを3つ取り上げ、それぞれ深く考察していきましょう。
考察1:褒めているように見せかけて本音を伝える技術
京都人の会話には、一見褒めているようで、その裏に本音が隠されている表現が多用されます。
たとえば、「お嬢さん、ピアノが上手ですね」という一言には、「音がうるさい」という真意が含まれている場合があります。
このような表現は、相手に直接的な不快感を与えず、関係性を壊さない工夫がされています。
私がこの技術に感心したのは、相手に行動を促しつつ、相互理解を深めるきっかけを作れる点です。
直接「うるさい」と言えば衝突が生じますが、間接的な表現なら相手に気づきを促す余地がありました。
また、著者は「褒め言葉を利用することで、リスクを回避できる」と述べています。
たとえば、職場で上司に「〇〇さんの合理的なご指摘はいつも助かります」と伝えながら、「その指示が曖昧であった」とほのめかすことで、間接的に意見を述べることができますね。
こうした褒める形を取った本音の伝え方は、日本の文化や職場環境にも非常に馴染みやすいと感じました。
考察2:遠回しな質問で相手に考えさせる技術
京都式コミュニケーションの特徴的な手法として、「疑問形を使って伝える」方法が挙げられます。
この手法は、直接的な指摘を避けながら、相手に問題意識を持たせるものです。
たとえば、「ドアを開けっぱなしにしていると、誰か来るの?」という疑問形は、「ドアを閉めてほしい」という意図を暗に伝えていました。
私はこの手法を「言葉の緩衝材」として非常に有用だと感じます。
ストレートな命令では相手に反感を持たれる可能性がありますが、疑問形を使えば、相手に「自分で考える余地」を与えることができますね。
また、この方法は家庭や職場など、あらゆる場面で応用可能。
たとえば、子供に「宿題終わったの?」と尋ねるのも一種の疑問形です。
直接的に「宿題をやりなさい」と言うよりも、相手が自発的に動く可能性が高まるでしょう。
本書では、遠回しな表現が「相手のプライドを傷つけずに済む」点が強調されています。
確かに、自己主張をしたい場面でこのテクニックを活用すれば、より柔軟で円滑なコミュニケーションが期待できると思いますね。
考察3:オウム返しで受け流す技術
不躾な質問やセクハラまがいの発言に対しては、ストレートに反論するよりも「オウム返し」で対応するのが効果的です。
たとえば、「子供いないの?」と聞かれた場合、「子供いないの?っておっしゃいましたね」と返すだけで、相手に「その質問が適切か」を考えさせる効果があります。
この技術の魅力は、直接的な対立を避けながら、相手に反省を促す点にあります。
私もこの方法を実践してみたところ、相手が戸惑い、自分の質問の不適切さを認識する姿を目にしました。
本書では、「相手にじわじわ効く毒を仕込む方法」として、この技術の意義が語られていました。
重要なのは、ただ反論するのではなく、「その発言が適切かどうかを相手自身に考えさせること」。
また、オウム返しは、相手との会話を断絶するわけではなく、あくまで関係性を維持しながら自分の立場を守るためのツールとして機能します。
特に、現代のハラスメント問題を背景に、こうした「エレガントな拒絶」の技術は、職場やプライベートの場でますます重要になってくると感じました。
まとめ:伝え方を変える3つの知恵
『エレガントな毒の吐き方』を通じて学べる伝え方の知恵は、以下の3つに集約されます。
1. 褒めながら真意を伝える
直接的な表現を避けつつ、相手を褒める形で伝える技術は、どのような場面でも役立ちます。
特に職場や家庭のような、関係性が壊れやすい環境では効果的ですね。
2. 質問形式で柔らかく伝える
遠回しな疑問形を活用することで、相手に気づきを与えながらも、柔らかい印象を与えます。
これは、日常生活やビジネスの場でも応用できるコミュニケーション術ですね。
3. オウム返しで受け流す
不躾な質問やセクハラ発言には、オウム返しで相手に考えさせる方法が有効。
真っ向から反論せずとも、自分の立場を守りつつ、エレガントに対応できます。
本書に紹介されたテクニックは、単なる嫌味ではなく、「相手との関係を大切にしながら自己表現をする方法」として捉えられました。
現代社会におけるコミュニケーションの難しさを感じている方にとって、これらの知恵は実生活で役立つはずです。
ぜひ本書を手に取り、自分自身の「伝え方」を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
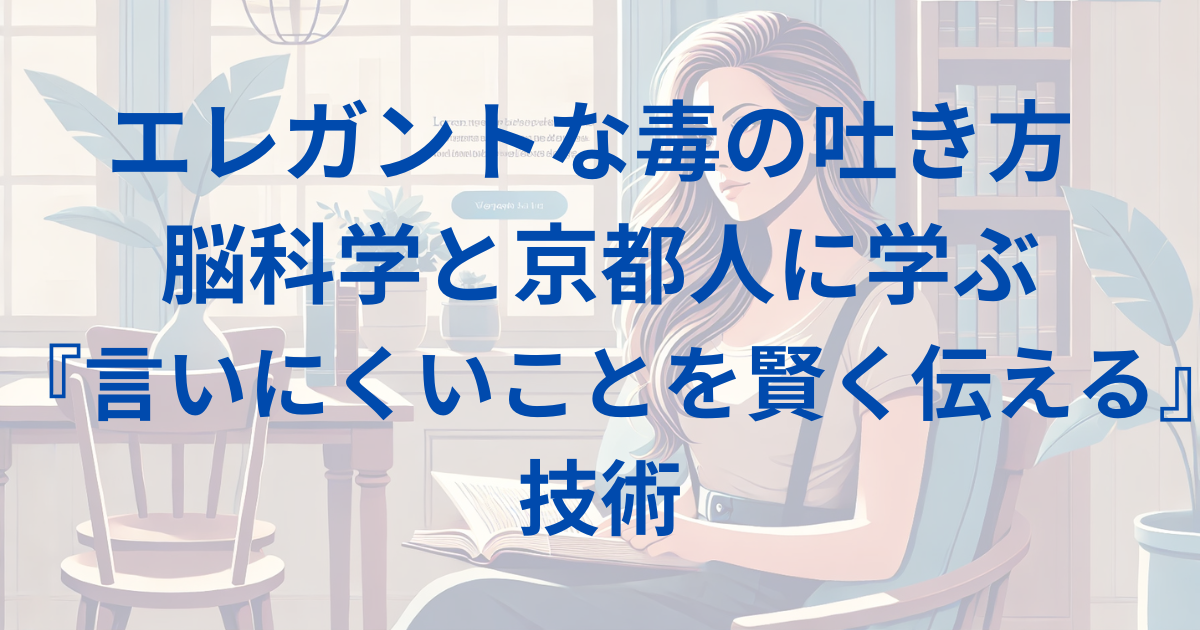
コメント